社会人としてのキャリアを始める、と聞いて多くの方は新卒一括就活をイメージするでしょう。しかし、実はキャリアの始め方はそれだけではありません。ベンチャー企業は通年採用を行っていますし、なんなら自分で会社をおこす選択肢も用意されています。特に研究者は専門的な知識や技術をシーズとして起業できる強みがあります。
実際に、大学発ベンチャーは近年勢いを増すばかりです。経済産業省が実施した「令和5年度大学発ベンチャー実態等調査」において、2023年10月時点での大学発ベンチャー数は4,288社と、2022年度に確認された3,782社から506社増加し、企業数及び増加数ともに過去最高を記録しました。しかしながら、いざ研究者が「自分の研究シーズを社会実装するために起業するぞ!」と考えたときに相談できる相手はあまり多くない、という現状があります。そこで、tayo magazineでは研究シーズをもとに起業した研究者・スタートアップへのインタビュー記事をシリーズ連載し、研究者がシーズをもとに起業する際の参考にしていただければと考えています。
今回は、腸内細菌による食の個別最適化を通じた健康社会の実現を目指すベンチャー企業であるBitaPの千葉のどかさんにお話を伺います!
インタビュアー (株式会社tayo)

熊谷 洋平
2018年、東京大学大気海洋研究所にて博士(環境学)を取得。専門はバイオインフォマティクス、微生物の代謝とエネルギー利用など。博士号取得後は株式会社フリークアウトにて機械学習エンジニアとして勤務。その後、国立研究開発法人海洋研究開発機構に移り深海微生物学者として研究する傍ら、2019年5月に株式会社tayoを設立、2021年7月に専業化。
インタビュイー (BitaP 千葉のどか さん)

代表 千葉のどか さん
2025年3月に東京科学大学博士課程にて博士号を取得。腸内細菌叢とウイルス性白血病の関連性の解析や、ブラックアイボリーコーヒーを生産するゾウの腸内細菌叢の解析をテーマとした研究を行っている。腸内細菌による食のパーソナライズの実現を目指して、まずは学術研究に基づく体質改善のための献立提案事業で起業予定。
※記事公開時点では起業済みです。
記事を書いた人

森 優希
ラプサンスーチョンという紅茶を飲むたびクセの強さに驚いているが飲み続けるとハマってきた。
千葉さんと腸内細菌研究
本日はよろしくお願いします。腸内細菌による食のパーソナライズで起業するとのことですが、そもそも千葉さんが腸内細菌の研究を始めたきっかけをお伺いできますか?
もともと「身体にいいごはんが作りたい、身体にいいごはんは何か知りたい」という気持ちが大学進学前からずっとあって、農学部や食品系の資格がとれる学部に進みたいと考えていました。
当時進学先の一つとして検討していた東京工業大学 (当時) のイベントで生命科学系の先生によるプレゼンを聞いたんですよ。そこで登壇されていた微生物の研究者である黒川顕先生のお話に感銘を受け、腸内細菌の研究をしたい!そのために東工大に進学しよう!と決意しました。
農学とかのイメージが東工大にないので進学先候補にあったのは意外、みたいなところはありますね。黒川先生のプレゼンって具体的にどんな内容だったんですか?
ヒトの腸内細菌には血液型のように様々なタイプ (エンテロタイプ) があり、それを応用することで個々人のエンテロタイプに最適なヨーグルトが作れる可能性がある、という内容でした。この話を聞いたとき、腸内細菌の研究を応用することで身体にいいごはん、それぞれの人の健康状態にあわせたごはんを作れるんだ!と気づきました。
なるほど。千葉さんが受験生だった時期はちょうどメタジェンが創業したり「腸内フローラ」というワードがメディアに出始めたりした時期と重なってますね。たしかに当時腸内細菌の研究やってたのは東工大か慶応くらいだったはず。
黒川先生のラボで研究をしたい!と他の学科に目もくれず受験勉強に励み、東工大に入学したら黒川先生は遺伝研に移籍なさってました。
そういうのアカデミアあるあるっすね。
入学して本当にすぐ黒川先生にメールして、遺伝研に移籍なさったことを知りました。そのメールで現在の指導教員である山田拓司先生を紹介していただきました。それが縁で学部1年の頃から山田先生のラボに足を運ぶようになり、アウトリーチ活動などのお手伝いをさせていただきました。

千葉さんの研究テーマについてお伺いしようかなと。やはり当初の関心である健康や食を前提にしてテーマを選ばれたんですか?
本当はそうしたかったですね。研究テーマはウイルス性白血病を患った患者さんの腸内細菌の解析でした。食べ物にかかわるテーマにできないか、と一回交渉はしてみたんですが、食事摂取のデータがなくてダメでした。
もともとヒトの腸内細菌と疾患・健康にかかわるテーマであればまずはよかったので、このテーマには意欲的に取り組んでいました。しかし栄養や食とヒトのかかわりについて学びたい、研究したい気持ちはずっとありましたね。
そうすると栄養学はご自身で学ばれたんですか?
専門分野だなんていえるほどではないですが独学しました。3か月ほど医薬基盤・健康・栄養研究所という国立研究所で、大学の制度を利用したインターンのような形で研修させていただきました。そこでは栄養学の基礎やデータ解析、栄養学の研究者とコミュニケーションをとる、という経験をさせていただきました。管理栄養士の方が行う栄養計算についてもそのしくみを学び、実践もしました。
起業という選択肢
4月から山田先生のラボで研究員をしながらご自分の事業も進めているとのことですが、起業も含めた千葉さんのキャリア観っていつ頃形成されたんですかね。
実は起業という選択肢は山田先生にお会いしたころ、それこそ学部1年のころにもらっていました。先生が起業されていたのもあり、結構軽いノリで起業をすすめられましたね。
たしかに山田先生のところの出身で起業された方知ってます。千葉さんの中で起業という選択肢が具体的になったのはいつ頃ですか?
とあるビジネスコンテストで賞をいただいたとき、起業いけるかも?と思いはじめて、2024年の1月に起業しよう、と明確に決めました。実は腸内細菌系のスタートアップに就職するか起業かで迷っていたんですが、最終的には起業という選択肢をとりました。
なんで起業を選んだんでしょう?
ビジョンが一番近かったのがその会社だったんですが、その会社では食べ物の事業が走っていなかったんです。一番やりたかったのは食べ物のデザインだったので、やりたいことを少しでも早くできる方法として起業を選択しました。
食べ物 x 腸内細菌やっているところもいくつかあるのでは?
色々お話は聞いたんですが、私のやりたいこととはちょっと違うなあと思いました。どうしても腸内細菌系の企業だと検査会社の色が強くなってしまうんです。
食べ物を作りたいんすね。
はい。レシピ提供などすぐ食べられない形での事業はやりたくなくて、お客さんのところに食べ物を届けたいです。店舗を持つことも考えたんですが、利益率が低いこともありなかなか初期には取り掛かれなそうだと思っています。今は、社員食堂などの監修に入るなどの事業展開を検討中です。
フードテックで市場を切り開くための千葉さん流戦略
そもそもフードテックの難しいところとして、原価率が高いから検査やデータ解析などの間接業だと事業が成り立たない、というところがありますが、千葉さんが事業展開するうえでの戦略は何かありますか?
まだ考えている最中ではあるんですが、ひとつはtoB、toCの両輪でやることですね。toCでの事業展開として、腸にやさしいお弁当を作って売る、というのがあったんですよ。それで実際に売ってみたらめちゃめちゃ赤字で、「これだけではビジネスとしてやっていけない」と思いました。
toBのほうはコンサルティングや情報提供ですね。こちらは利益を上げることができます。こちらも単なる案件にとどまらず、社員食堂を運営する会社の課題がわかるのはとても面白くやりがいがあります。課題がある中で、自分が価値提供できるポイントを見つけていく楽しさがあります。
最近は健康経営みたいなのも流行っているので、福利厚生みたいなところに入っていく感じでしょうか?
腸内細菌だとあと3年から5年くらいは目新しいイメージでいけるかな、と考えているので、そういう視点から健康経営という観点で興味を持ってもらえるかと。
現在の社員食堂向けのモデルでは、具体的にどのような価値提供が可能なんでしょうか?
レベル別に3つあります。レベル1は社員食堂の運営会社のブランディング向上、レベル2は食事に機能性をもたせる、レベル3は個別最適食の提供です。
レベル1は今もやっていますね。社員食堂の運営会社にとっての訴求ポイントは健康ですよ、おいしいですよ、という2つがメインです。そこに「腸内細菌の研究者が監修!」とつくことで差別化できる。
たとえば発芽玄米を使用した献立で腸活フェアを開催するとします。そのとき私がやることとしては、発芽玄米が腸内細菌にどのような効果を与えるかについて調べた論文を探して、ポップに解説文を書く、というところですね。
レベル2は表記の課題がありますが、企業のニーズをかなえられるような機能を備えた食事の監修や献立の提供ですね。以前、工事現場の作業員を抱える企業から「午後のパフォーマンスを向上させるような食事を提案してほしい」と言われたことがあるんですよ。他には離職率を下げるためにメンタルを安定させられる食事の提案をしてほしい、という依頼もありました。
レベル3では、それぞれの身体のデータにあわせて「A、B、Cという3つの定食があるが、あなたにおすすめなのはA定食」「あなたにおすすめな小鉢の組み合わせは切り干し大根とほうれん草のおひたし」のように個別化した提案を行います。データとして使いたいのは腸内細菌、血液、健康診断の結果などを考えていますが、まだ何を使うか明確に決まってはいないです。
イメージがわいてきました。一方、機能性の食事を考えるうえでベースになるのはあくまでPFCバランスなどの栄養学なのではないかという気がするんですが、腸内細菌の考慮によって機能性に与えるインパクトは向上するものなんでしょうか?
正直なところ、ちゃんと検査をしないと食事の機能面における腸内細菌の価値ってそんなにないんですよ。
たとえば腸内細菌の特徴がA、B、Cの3種類あり、Aではりんご、Bではみかん、Cではパイナップルが血糖値を下げるのに有効というデータがあるとします。それらすべてを材料としたフルーツポンチを提供すれば、含まれているフルーツのうちどれかひとつはそれぞれの腸内環境に働きかけ、血糖値を下げる効果を期待できます。
このような形だと腸内細菌的に意味をもたせ、なおかつ機能性をもたせられるので、腸内細菌を考慮する意義が出てくると考えています。
ここまでお話を伺っていて、検査会社にするよりは食事を提供したいという思いは伝わってきました。しかし検査をしないと食事の介入効果はわからないし、検査にはお金がかかる。検査やデータ収集の方針など現段階で決まっていますか?
現段階ではその問いに対して明確な解はないですが、未来に希望を持っています。ここ10年の動きをみると、時間の経過とともに検査にかかるコストや時間は減少していますし、3年くらい経てばBitaPの事業にとっていいことがあるのかな、と考えています。逆に今から検査技術を開発しようとしてもいいものは作れないので、そこは先人におまかせしようかなと。
プランBとして、必ずしも腸内細菌にこだわらない方向へのシフトも考えています。実は腸内細菌ってヒトの身体の状態をはかるうえで今はまだそこまでよい指標ではないんですね。血液のほうがよほどよい指標になるんです。たまたま今の強みが腸内細菌なのでそちらを押し出していますが、よりよい指標があればそちらにピボットすることも考えています。腸内細菌屋さん、というよりは食事屋さんとしてやっていきたいです。
技術はピボットしづらいですね。腸内細菌の検査系を立ち上げるとそれ以外のことがやれなくなってしまう。既存の腸内細菌関係の企業とは協業していくような方針なのでしょうか?
はい。彼らには何度も話をうかがったのですが、検査技術を作るのに10年くらい時間をかけているんですね。彼らの研究開発の成果を落とし込んだプロダクトのようなものが考案できれば協業できるのではないかと思っています。
大学発ベンチャーのエコシステムにスモールビジネスの風を
起業するためにこれまで様々な学内外の支援を受けてきたと思いますが、創業に至るまでに受けた支援でよかったもの、転機になったものはありますか?
それでいうと学内のスタートアップ支援 (東工大スタートアップチャレンジ) ですね。申請書の内容によって金額が変わるタイプのもので、最大100万円もらえるんですが私がもらえたのは32万円だったんです。最初は「なんだ100万じゃないのか」と思いましたが、よく考えると32万円って微妙に手にしたことがないレベルの大金だったんですよ。「じゃあ手元にあるこの32万円で何ができるか?」を考えて、ヒアリングしたりお弁当を作って販売したりしましたが、それで自分の事業を次につなげ、会社として成長する種を作ることができました。下手に100万円もらっていたら「倫理審査通して腸内細菌のデータをとるぞ!」と浮足立ったことをしていたと思います。
これすごくいい話ですよね。一旦スモールビジネスとして立ち上げ、コンサル的な知見提供などで黒字化するのはとても大事だと思います。現場感を学ぶのは大学発ベンチャーのアントレ教育に足りない要素の気もします。
そういうのめっちゃ必要じゃないですか!? 熊谷さんのおっしゃるように、大学のアントレプレナー教育で教えてくれるのってヒアリングどまりなんですよ。現場に行くとかプロダクトを作って売るところまでは誰も教えてくれない。あと大学からのお金なので資金用途も限定されていて、営利行為への支出がNGだったんですよ。この経験を通じて大学のお金で受けられる支援への解像度はすごく上がりました。
基本的にはスタートアップ政策が最上段にあるので、大学発ベンチャーのエコシステム内にスモールビジネス起業を促すモチベのある人が誰もいないんですよね・・・。
私も本当にそう思います。「私はディープテックの人」みたいに思っていた時期が2年くらいあったんですが、それで時間を無駄にしたところはありますね。
クラファンの後どうするか
千葉さんはクラファンもやられていますね。クラウドファンディングで資金を集め、イノベーティブなスモールビジネスを展開するのはいい流れだと思ってます。
クラファンだと普通に資金調達をするのとは異なり、事業を通して実現したいと思っている世界を多くの人に知ってもらえるんですよね。私の場合は腸内細菌を活用した個別最適食によって誰もが毎日元気に過ごせる社会を実現したい、という思いがあったので資金調達の手段としてクラファンを選びました。クラファン終了後はデータベースの作成を通じて機能性ごはんや個別最適食の実現に取り組みます。
クラファンの話も出たことなので、せっかくならクラファンのお話も聞かせていただきたいですね。もうそろそろ達成できるか、くらいの感じですよね。
いま (取材当時) の達成率は92%くらいですね。
個別最適食のデータベース、という発想はあんまりないものなんですか?病院食の献立を考えるためのデータベースはありそうですが。
なくはないと思います。ただ、聞いた話だと病院食の献立は管理栄養士の方の知識と経験をベースに考えられているそうです。正直なところ、私が作ろうとしている個別最適食データベースは管理栄養士さんの仕事を一部奪うようなものなんですよ。なので、管理栄養士の方をサポートするような方向性に持っていきたいですね。
※記事執筆時点でクラファンの目標金額を達成したとのご連絡をいただきました!おめでとうございます!

データベースについて
データベースが大事なのはすごくわかります。ただ、どの情報をインプットしたらその人に最適な献立が出力されるか、というのは難しそうですね。そのあたりはどういうお考えでしょうか?
個別最適食のところは重要ではありますが、まだまだ様子を見ながら、という段階ですね。現在は腸内細菌データをインプットにしていますが、適切なパラメータにならない気もしています。
機能性ごはんという観点であれば、ある食品に含まれる栄養素にどのような効果があるか、腸内細菌という観点でどのような効果がうたえるか、腸内細菌のタイプごとに特定の効果がある食品は何か、をまとめています。具体的には、りんごに含まれるペクチンをある腸内細菌が利用して血糖値が下がる、という効果がこのようなメカニズムで発生する、ということを示した論文をもとに対応表を作成する感じです。
KNApSAcKデータベース (注1) みたいな話ですね。かつてこのようなデータベースを作るのはめちゃくちゃ大変でしたが、LLMによってある程度ハードルが下がっているところはありそうです。ただインタフェースを決めないと、どういう情報をどのような形式で持つか決まらないのが難しいですよね。
最初は大きなスプレッドシートでいいのでは、と思っていましたが、データベース形式にして検索エンジンのような形で使えるものを作ろう、という段階にきています。
でも食品メーカーや一般ユーザーがほしい情報というのはまだまだわからないので、顧客の要望を聞きながらどのようにするか考えている最中です。ある会社にヒアリングしたとき、この成分を安定的に供給できる工場はあるか、価格はどれくらいか、が出力されるとうれしいという要望を聞いてなるほど!と思いました。
手出しの調査で得た情報をどのように蓄積するかは大事ですよね。ただ、血の通ったデータをどのようにデータベースと紐づけるかという課題も出てくると思います。千葉さんのやりたい事業としては独自のシーズをデータベースに置きたい、という話でしょうか?
それをデータベースに置きたい、というのはありますし、それより先が現段階では見えていないほうが近いですね。データベースがあれば機能性ごはんやお腹にやさしいごはん、さらには個別最適食を作れるようになるだろうと考えていますが、「あれ?違うかも」という瞬間がくるかもしれないです。
(注1) KNApSAcKデータベース: 植物や微生物における二次代謝産物 (生命活動に必須ではない二次代謝の結果産生された化合物) の分子式、分子量、同定された生物種名、実験によって得られたマススペクトル解析結果をとりまとめたデータベース。インターネット上で無料公開されている (https://www.knapsackfamily.com/KNApSAcK/)。
(注2) LLM: Large Language Model (日: 大規模言語モデル) の頭文字をとったもの。大量の文章データと深層学習技術によって構築された言語モデルであり、ChatGPTなどの生成AIツールにも活用されている。
今後の事業展開
データベースを作り、社員食堂などの業界構造を見たうえでどちらに行きたいか、など現時点で何か案はありますか?
仮に社員食堂の運営会社を主な顧客としたとき、中小だと3,000社くらいの運営会社があるんですよ。そのすべての監修に入ってしまうと差別化ができなくなってしまうので拡張可能性に問題があるのと、営業を頑張らないといけないというビジネス的な課題もあります。
後継者がいない食品系の会社の事業継承をして、腸内環境を整えるという付加価値をつけてお弁当を販売する、、とかもあり得そうですね。そうするとテクノロジー関連の補助金も取りやすくなりそう。
そうすると私としては食品提供の拠点ができるし、先方としても経営が改善して両者うれしいことになりそうですね。これまで全くない視点でした。
BitaP紹介
今回インタビューした千葉さんが代表を務めるBitaPは、一人ひとりに最適な食事(個別最適食)を通じて、誰もが健康で充実した毎日を送れる社会の実現を目指す団体です。法人としての設立を考えているとのことです!
※記事執筆時点では設立予定でしたが、公開時点では設立済みです!
https://sites.google.com/view/bitap-health

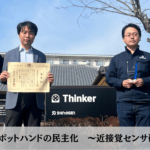



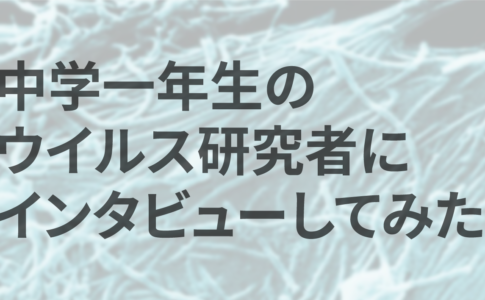
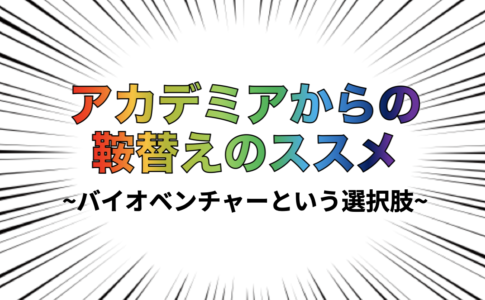

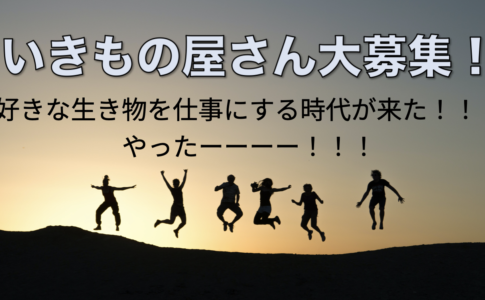
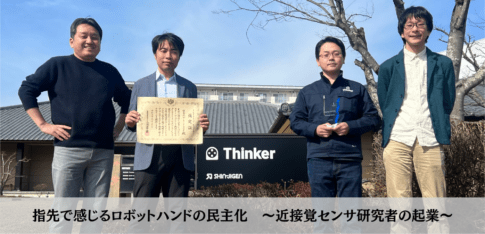
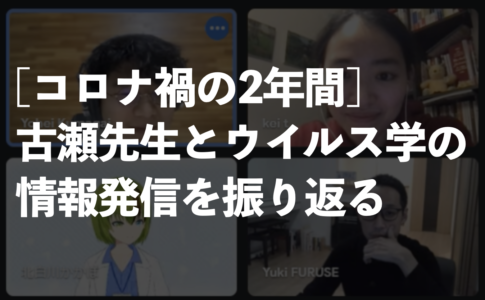

最近のコメント